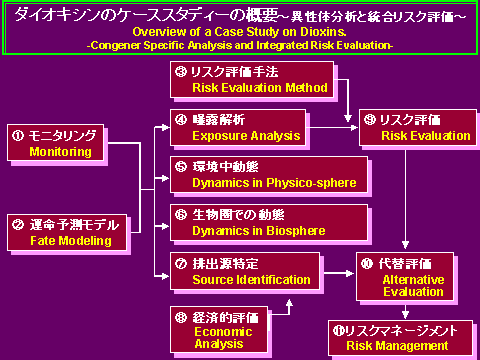
図1
(2000.1.27)
本研究プロジェクトの到達点:ダイオキシン研究の紹介
中西準子
1.ダイオキシンケーススタディの全容
本研究プロジェクトでは、化学物質の使用に伴う人の健康リスク評価、生態リスク評価、ベネフィット評価をし、最終的にリスクとベネフィットのバランスをとることによって、化学物質の管理に必要な理論的な枠組みを提供することを目的にしています。
基本的な目標は、リスク評価手法の開発を含む理論的な枠組みの構築ですが、平行して、ダイオキシン、DDT, ベンゼン、内分泌攪乱物質、水銀、室内汚染物質などについてのケーススタディーを行っています。
生態リスク評価についても、大きな進歩がありましたが、ここでは、時間が限られているので、特に人間への健康影響に焦点をあてて、ダイオキシンの研究結果を報告します。
この報告では、ダイオキシンとは、PCDD(ポリ塩化ジベンゾダイオキシン)とPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)の集合です。Co-PCBを含めるときは、ダイオキシン様化合物(D-likeと略す)と言います。congenerを、日本での理解の容易さを考えて、異性体と訳すことがあります。
ダイオキシン研究の全容を図1に示します。
我々の研究の特長は、異性体の違いに注目していること、異種のリスクを統合的に評価する方法を開発し、それを使っていることです。
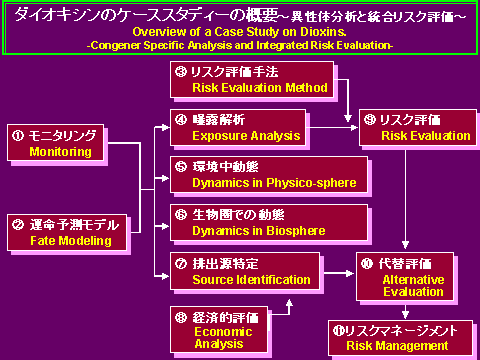
図1
2.ダイオキシンによる曝露とリスク
2.1 曝露解析とシナリオ
まず、人がどのようなルートでどの程度の量、ダイオキシンを体にとりこむかを調べました。これを、曝露解析といいます。
一般人(G)、焼却炉周辺住民(LR)、魚介類多食者(HFC)の3グループを対象にしました。一般人とHFCについては、国の機関等による測定値を基に推定しました。
LRについては、濃度予測の数理モデルを構築し、それを用いて解析を行いました。LRは、茨城県城取清掃工場から1km以内に30年間居住し、野菜類はそこで栽培されたもののみを食べているというシナリオです。
城取清掃工場から、主風向風下1km以内での土壌中ダイオキシン濃度の測定値(宮田秀明ら、1997)を基に、逆に大気濃度と、そこで栽培された野菜類のダイオキシン濃度を推定して、曝露量を推定しました。これは、環境条件としてはworst-scenarioで、これほどひどい条件下で生活している住民は存在しないと思います。
曝露解析の結果は、省略します(Chemosphere、Vol.40、NO.2、pp.177-185,2000)。ダイオキシンは基本的に食物から摂取していることが分かります。
2.2 YNFの提案
日本人が、ダイオキシンを主として食物から摂取していることを、別の角度から証明できないか、私はこう考えました。そのために、食物の異性体分布と体内蓄積の異性体分布が一致するどうかを検討しました。一致しなければ、別の曝露ルートがあるに違いないと思ったのです。
そのために、厚生科学研究で行われている total diet study の研究結果を利用しました。total diet study というのは、日本人の標準的な食事中に含まれる成分を調べる研究です。
厚生科学研究で、1977年からのデータが発表されています(豊田正武ら、1999)。1977年から1996年まで20年間、total diet studyの食事をしたと仮定したときの、体内蓄積ダイオキシン類と、1998年の母乳中ダイオキシンのcongener 分布と比較しましたが、その結果は一致しませんでした。
しかし、これは当然なのです。ダイオキシン類の体内での挙動はこれまで異性体によって変わらないと仮定していますが、その仮定が違うのです。
図2に示すように、4異性体があったとして(現実には136あるのですが、)皆同じ濃度で排出されても、環境中での動態が違い、また、人の体内での利用能が異なるので、その相対的な量は、体内では違ってしまうのです。

図2
今、問題にしているのは、食物から人の体内ですから、異性体による人の体内での利用能を考えなくてはならないのです。
利用能は、体内半減期と腸管での吸収率の積に比例します。この二つを、用いて生物学的利用能の相対比を求め、それをYNF(yoshida-nakanishi factor)と名付けました。結果は表1です。
表1

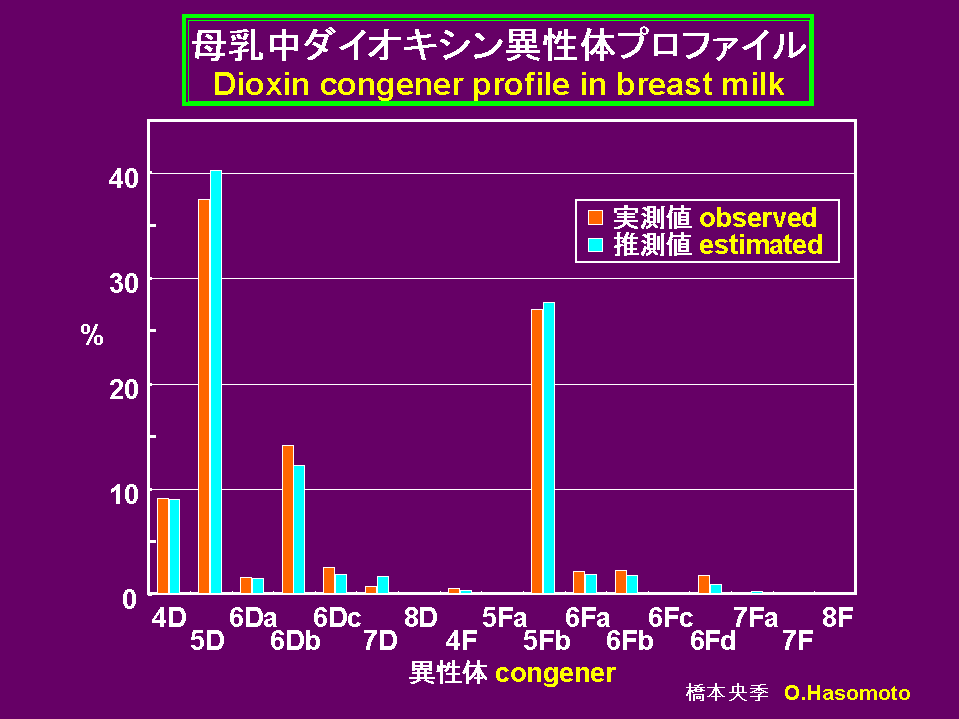
図3
20年間摂取したものと体内蓄積ダイオキシンの異性体分布は、YNFを考慮すると、図3のように驚くほど、一致するのです。
表1を見ると、PCDDs(ジベンゾダイオキシン)のYNFはPCDFs(ジベンゾフラン)のそれに比べ大きいことが分かります。フランの4塩化物のYNFは0.06です。食物中には多いですが、人体内には残らないのです。
フランはジベンゾダイオキシンに比較して分解しやすいので、TEFの推定値より、実はリスクが小さいのです。焼却炉から出るのは、どちらかと言えば、フランが多く、農薬はジベンゾダイオキシンが多いです。農薬起源のダイオキシンの方が、人の体内に長く残存し、それだけ、リスクも高いのです。
今使っているTEFでは、このことは表現されていません。リスク評価では、TEFではなく、TEFとYNFの積が用いられるべきです。
YNFを求めようと思った最初の動機は、食物以外の大きな曝露経路があるか、見落としていないかをcheckするためでした。YNFの導入で、一致したので、食物以外の大きな曝露経路の見落としはないものと考えています。
2.3 日曝露量を尺度にしたリスク評価
つぎに、日摂取量(曝露量)をもとに人の健康へのリスク評価を行いました。発がん、生殖影響、子宮内膜症、また、胎児・乳児の神経行動への影響を評価しました。これらの評価については、不確実性の解析を行っています。
WHOや日本政府は、ダイオキシンは発がんのpromoterであるから、用量反応関係で閾値があるという解釈をしています。この立場を認めると、発がんリスクは限りなくゼロに近くなります。
しかし、米国環境保護局は、Ahレセプターを経由したactivatorであるという考え方もありうるとして、閾値なしの考え方を捨てていません。そして、この仮定の下で得られた結果と疫学調査の結果から、10-4{pg/kg/day}-1の発がんポテンシーを仮提案しています(1994, 1997)。
この考え方に依拠し、閾値なし(直線近似)の仮定を用いて算出すると、ダイオキシンによる一般人、LR、HFCの生涯発がんリスクは、10-4のレベルとなります。これは、削減すべきレベルですが、一般にあるものと比較して、極端に高いわけではありません。子宮内膜症のリスクはゼロに近いですが、胎児、乳児の神経行動リスクは、より詳細に検討すべきです。
3.胎児・乳児のリスク評価
3.1 胎児リスク
2節の結果をうけて、胎児、乳児のリスク評価を、より詳細に、実態に即して行いました。
主な改良点は以下の通りです:
1)日平均摂取量ではなく、母親の体内蓄積量を尺度とし、実測値を使う。
2)TDIをダイオキシン類とCoPCBの総TEQで4pg/kg/dayと決定した時(1999)に、日本政府が用いた毒性データを用いることです。
具体的には、エンドポイント(影響を見る事象)を、免疫不全関連バイオマーカーの変化としたこと、最小影響量(LOAEL)を母体内蓄積量86ng/kg、不確実性係数を10としたことを、踏襲しました。
多田裕氏らの、415人の母乳中ダイオキシン類濃度のモニタリング結果(1998年度厚生科学研究)を基に、図4に示すような手順で、日本人母親の体内負荷量の分布を推定しました。
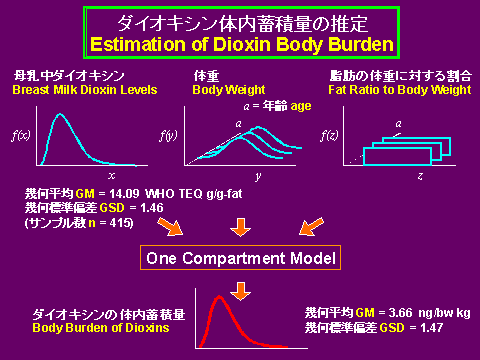
図4
結果は、PCDD/Fsの体内蓄積量は、WHO-TEQで、幾何平均値が3.66 ng/bw
kg、幾何標準偏差1.47、(PCDD/Fs+Co-PCBs)のそれは、幾何平均値6.29で、幾何標準偏差は1.45で、いずれも分布形は対数正規分布です。
つぎに、国は図5に示すように、LOAEL値を不確実性係数10で割って、8.6ng/kgを許容体内蓄積量とし、日平均摂取量に換算してTDIを出しました。
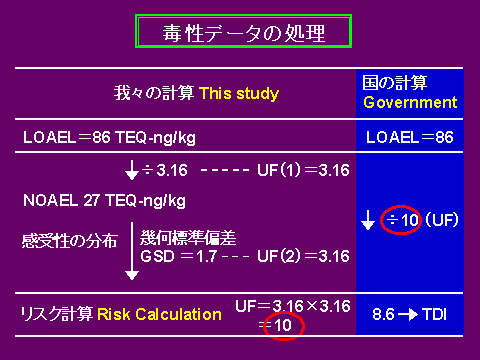
図5
今回の我々の研究では、国と同じ仮定でリスクを計算することにしました。その方が、理解が容易だと思われるからです(この仮定が必ずしも妥当だと思っているわけではありませんが)。
まず、LOAELを3.16で割って、無作用量を求めました。つぎに、胎児集団の感受性の個人差は、幾何標準偏差1.7と仮定しました。これは、不確実性指数=3.16に相当するものです。3.16×3.16=10で、これで、国の仮定(不確実性指数10)と同じになるのです。
最も敏感な胎児を対象にした影響をendpointにした結果であるので、胎児集団内の個人差の不確実性指数は、3.16で十分だとされています。
TDIを決めた時のendpointは、実験動物での免疫系の異常を示すバイオマーカーの変化であり、人への直接的な影響と結びつけることができるか否かは、今後の検討課題です。
しかし、ここでTDI決定の際、用いられたので、本研究でもこれをエンドポイントにしました。これは、ダイオキシンの蓄積性などを加味した、安全側の配慮です。通常のリスク評価では、このようなエンドポイントを用いることはありません。
このような条件下で、曝露の余裕度、MOE(Margin of
safety)=”NOAEL/体内蓄積量”と、定義します。この値が大きければ安全ということになります。また、1ならば、丁度NOAEL、1以下なら、病気が発生するということを示しています。
リスクは、体内蓄積量が、このNOAELを超過する確率で定義します。体内蓄積量にも高い人から低い人まで分布がある、NOAEL、つまり感受性にも分布がある。この二つを組み合わせた時、体内蓄積量がNOAEL以下になる確率を、MONTE Carlo simulationで求めます。これが、その結果です(図6)。
リスクは、PCDD/Fsについては、おおよそ10-3、(PCDD/Fs+Co-PCBs)については、2×10-2となりました。
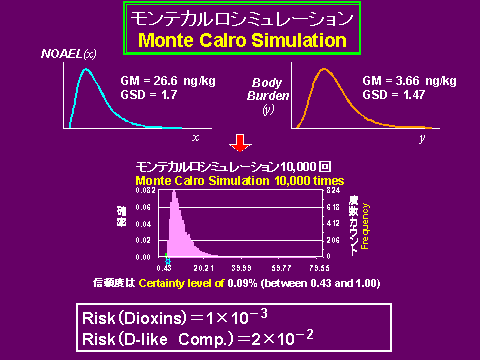
図6
3.2 授乳によるリスク
つぎは、授乳によるリスクです。授乳による悪影響を警告した論文は多くありますが、いずれも用量・反応関係は明確ではありません。Hoover(1999)がまとめているように、授乳による影響はありますが、その大きさは胎児に与えるリスクよりは小さいと言えそうです。ここでは、授乳によるリスクは、最大胎児リスクに等しいと評価しました。
Hooverは、母乳中のダイオキシン類を含む、15のPOPs(残留性化学物質)の授乳による発がんリスクを計算しています。その大きさは、平均で2×10-4です。
4.リスク比較
ここから、我々の研究の主題、ダイオキシンリスクをどのように管理するかに移ります。我々は、リスク便益解析に基づいて管理すべきと主張しています。しかし、実践的な見地から、以下の手順を踏んで、リスク便益解析に到達した方がいいと考えています。
1)他のリスクとの比較とある種の目標値との比較
2)代替案の評価
3)リスク便益解析、または費用対効果分析。
4.1 リスク比較の道具−損失余命
ここまでは、リスクをあるendpointの生起確率で示しました。しかし、これでは異なるendpointのリスクの比較ができません。そこで、我々はendpointの重篤度を、損失余命(LLE)で評価し、確率と重篤度の積でリスクを評価(単位はLLE)し、比較することを提案しています。LLEの詳細は、蒲生昌志が報告しています。
ダイオキシンによるがんのリスクは、一般人で1.3×10-4です。がんの重篤度は、LLEで12.6年です。これは、我々が計算したものですが、がんになることは、平均して12.6年通常より早く死ぬことを表現しています。12.6年に1.3×10-4をかけると、0.6日になります。これが、LLEで表した発がんリスクの大きさです(表2)。
表2

4.2 メチル水銀の胎児リスク
つぎに、このLLEを用いて他のリスクと比較しましょう。
メチル水銀の胎児への影響は、ダイオキシンの胎児への影響と、そのメカニズムの点で驚くほど似通っています。母親の体内蓄積によるメチル水銀が胎児に移り、胎児に与える影響がcriticalであること、メチル水銀が主として魚介類の摂取で取り込まれることです。
メチル水銀の場合のendpointは神経障害で、二つの疫学調査から用量・反応関係が求められています。このリスクは、日本人の集団で3×10-3程度です。
すでにご存じの方が多いと思いますが、メチル水銀は、基本的に自然汚染です。このリスクは、先に計算したPCDD/Fsと(PCDD/Fs+Co-PCBs)による免疫影響についての二つのリスクの中間に位置します。でもendpointが違うので、確率で表現されたリスクを比較しても、どちらが大きいか分かりません。
そこでエンドポイントの重篤度を推定します。メチル水銀の神経症状のLLEは、水俣病のケースから、1.85年と我々は計算しています。したがって、このリスクは2日の損失余命ということになります(表2)。
では、ダイオキシンによる胎児リスクはどうでしょう?このエンドポイントは、免疫不全の可能性ですから、どの程度の重篤度とは言えません。
これは、今後の課題ですが、メチル水銀中毒のエンドポイントが1.85年ですから、ダイオキシンの場合、1年を見れば十分でしょう。そうすると、このリスクはダイオキシンで0.4日、Co-PCBを含む場合は、7日となります。
ダイオキシンだけだと、メチル水銀の胎児リスクより小さく、Co-PCBも含めると、メチル水銀よりかなり大きくなります。リスクは、このレベルであることを知ることは重要です。
4.3 Targetsの設定
リスクレベルに管理目標となるtargetがあり、それと比較して管理目標を設定できると管理が容易です。ここでは、そのtargetを設定し、対策の必要性の度合いを知る手がかりとします。
targetsを先に決めるということは、すべての事象が同じリスクであるべきだと考えることを意味します。しかし、現実は、等リスク原理で動かすことはできません。したがって、このtargetsあくまでも、仮の管理目標であり、最終的にはリスク便益解析の結果を用いるべきであると考えています。
我が国では、水道水中発がん物質や、大気中ベンゼンの規制で、10-5の発がんリスクが目標になっています。まず、これを基準にしましょう。10-5の発がんリスクは、LLEで0.05日(ほぼ1時間)です。
つぎに、細菌感染症などの急性死では、損失余命は35年ですから、そのリスクレベルが3×10-6の時、LLEで0.04日となり、これが、10-5の発がんリスクと同じです。
たとえば、LLEが1年のエンドポイントに対しては、10-4が、ほぼ同じリスクになります。バイオマーカーなどの場合は、これ以下でしょうが、最大、10-4となります。
これは、水道水中または大気中の物質についてのtargetsです。確率は違いますが、真のリスクは同じです。
これを、食品に適用するときは、約10倍高くするのが適当です。これを認めて戴くには、長い説明が必要ですが、結論を言えば、リスク/ベネフィット的な考えによるのです、簡単に言えば、食品の場合、リスク削減が難しいからと考えておいて下さい。私が提案するtargetsのまとめを、表3に示します。
表3

このtargetsは、今後様々なリスクについて、どうすべきかを考える時に使って頂けるものです。
4.4 targetsとの比較
つぎに、このtargetsとダイオキシンによるリスクを比較しましょう。成人の発がんリスクは、activatorモデルを使った場合、10-4よりやや大きいことは、すでに書きました。
targets値は、10-4ですから、このリスクはtargetよりやや大きく、対策を必要とすると言えるでしょう。promoterモデルに依拠すると、リスクはゼロに近いので、削減の必要性はないことになります。
胎児では、PCDD/Fsのリスクは10-3です。targetは10-3以上となっているから、target以内です。しかし、Co-PCBsを含む場合のリスクは、このtargetを遙かに超えます。
そもそも、このtargetは単一の化学物質を対象にしたもので、ダイオキシンとPCBの合計に対して適用することは、無理があります。しかし、TDIが両方を対象にして決められていることから、ここでは、単一の物質と考えることにします。そのように考えると、このリスクは、targetを大きく超えるので、何らかの対策が必要という結論に達するのです。
(同一の毒性機能をもつ混合物のリスク管理がどうあるべきかについては、また、別の機会に述べます。国は、TDIをダイオキシンとCo-PCBの合計に対して適用することにしましたが、その際、これが混合物で、単一の物質と異なる原理が用いられるべきだということも考えていなかったような気がします。)
5.対策の評価
以下の対策についての評価をしました:1)母乳をやめる、2)食品中ダイオキシンの規制、3)一般ごみ焼却施設の対策、これらは、いずれも現実に提案され、一部は実施されているものです。
母乳授乳をやめる政策が妥当か否かを判断するポイントは、母乳中ダイオキシン類のリスクが、母乳授乳をやめることのリスクより大きいかということです。ここでは、母乳授乳をやめることのリスク、逆に言えば、母乳授乳のベネフィットを算出します。
母乳授乳によるベネフィットは、morbidityと死亡率の減少及び神経系、免疫系、視力、肝臓機能、心身の発達へのよい影響が報告されています。ここでは、その内のひとつ、死亡率の減少のみを取り上げることにします。
この中で直接死亡につながるものだけで、呼吸器疾患、壊死性腸炎、突然死などがあります。Roganらは、母乳をやめることによる死亡率の増加は、2.6×10-3、損失余命で67.1日と推定しています。授乳のリスクの10倍近く多く、母乳をやめるという政策は、妥当ではないことを示しています。
食品に基準値を設定するという政策も、母乳の場合とほぼ同じ理由で、適当ではありません。
つぎは、ごみ焼却施設に対する対策を検討します。岸本充生・岡敏弘は、厚生省のごみ焼却施設対策の、費用対効果解析を行いました。
その結果は、1年・人の損失余命に相当するリスクを削減するための費用(CPLY)が、緊急対策で7900万円、恒久対策で5億4000万円と推定されました。
この計算の過程で用いられたリスク評価法は、初歩的であったため、現在さらに精密な方法で行っており、最終的な値とは言えません。しかし、一応この値が正しいとすれば、緊急対策は妥当ですが、恒久対策は、あまりに費用がかかりすぎて不適当と判断されます。
費用がかかりすぎるというだけではありません。リスクはそれほど急には低くはならないのです。
吉田は、焼却施設からのダイオキシン排出量の規制の効果を推定しました。27歳女性のダイオキシン体内負荷量の経年変化を、過去から未来に向けて予測することによって、この対策の効果を推定しました。
焼却からのダイオキシン排出が、1999年以降1/5に減少するとすれば、17年後に母乳中ダイオキシン量が現状の半分に減少すると予測されます、排出量を10分の1にしても、母乳中のダイオキシン量が半分になるのは、15年後です。
焼却施設に厳しい対策をとっても、その効果が直ぐに現れないのは、基本的にダイオキシン汚染が過去の汚染であること、主たる汚染源がごみの焼却炉ではないことに起因しています。
或いは、真の発生源をつきとめていないという懼れすらあるのです。実は、我が国では、ダイオキシンの85%は、一般ごみの焼却炉から出ているという説が流され、それを基にダイオキシン対策が立てれらました。しかし、本当はダイオキシンの発生源は全く調べられていなかったのです。
6.発生源の探索
6.1 主成分分析
リスクマネージメントにとって、最重要課題は発生源のinventoryを作成することです。これなしには、何も進まないのです。
特にダイオキシンは、製品でないので、発生源をつきとめることは難しいのです。さらに、source inventoryの作成のためには、“環境データ”から発生源を推定するための科学が必要です。
この課題の重要性に鑑み、我々の研究室では、この研究に10年間とりくんできました。本研究プロジェクトでは、ダイオキシンだけでなく、他の化学物質についても、“環境”から攻める方法論の開発に力を入れています。
すでに、一昨年、昨年のWSで益永が報告しましたが、ダイオキシンの発生源分析の方法と結果について、もう一度まとめておきます。
ダイオキシン類の中で有害なcongenerは17種なので、ほとんどの分析で17種の結果しか示されていません。しかし、無害成分を含む多くのcongenerのprofileがあれば、発生源情報を得られやすいと考えて、我々は、塩素数4またはそれ以上のcongener136のうち、87ピークを分離定量してきました。
そのために、分析に使っているカラムも他の分析機関のそれと異なっています。東京湾、霞ヶ浦、宍道湖の底質、河川底質、水田、都市土壌などの試料について、congener profileの分析をし、主成分分析にかけた結果、3〜4主成分が抽出されました。
第一は大気沈着、第二は水田除草剤PCP、第三は水田除草剤CNP、第四は未知成分でした。この解析は、無害成分も含めた解析なので、これだけでは環境中に残存する有害成分に農薬起源のものがあるという証拠にはなりません。
わが国で製造されたPCPとCNPにダイオキシン不純物が含まれていることは分かっていましたが、有害な成分が含まれているという報告はありませんでした。我々は、1960年代、1970年代に製造されたPCP、CNPを探しだし、分析して、古い農薬には高濃度の有害成分が含まれていたことを明らかにしました。
益永は、このデータを基に、1955から40年間のダイオキシン環境放出量を推定しました。除草剤起源のダイオキシン量(I-TEQ)は、一般ごみ焼却施設、産業廃棄物焼却施設からの排出量の、4倍を超えるという結果になりました。尤も、これは少ない試料数での推論なので、誤差は大きいです。
6.2 重回帰分析
現実に環境中試料TEQの中での、3主成分の寄与率を知ることは重要です。このために、我々は、それぞれの成分のcongener profileを求めて、重回帰分析で3主成分の寄与率を求めました(益永発表)。
宍道湖底質では、WHO-TEQで以下のような結果になりました。1965年堆積底質では、大気沈着、CNP、PCPの寄与率が、それぞれ14%、0%、86%、1993〜1994年堆積底質では、それぞれ、33%, 8%, 59%でした。
大気沈着の寄与率が、6.1節の推定値より大きいですが、このことは、我々がまだ、大気沈着の全容を把握していないことを示しているように思います。
宍道湖のデータは、一般ごみ、産業廃棄物以外の熱過程の排出源があり、それらの寄与は、1960から1970年代には今より大きかったとことを推察させます。尤も、この重回帰分析は、農薬試料数が少ないために、不正確で、この結果のみで決定的な結論は出せないことに、留意する必要があります。
6.3 水田中ダイオキシンの行方
益永の推計では、40年間に水田に散布されたダイオキシン(I-TEQ)は、CNPから190kg、PCPから400kg、計590kgとなっています。
ベトナム戦争で使われたAgent
orange中のダイオキシン量(I-TEQ)は、ほぼ170〜550kgと推定されていますので、その量と匹敵するか、或いはそれ以上の量の有害ダイオキシンがわが国の水田に散布されたことになります。
1970年代のわが国の水田作付け面積ほぼ300万haに、この量が均等に混入したとすると、水田土壌中ダイオキシン濃度は、約100pg/g of
soilと計算されます。1999年度環境庁の調査によれば、水田土壌中のダイオキシン濃度は、平均で51pg/g、最小値15、最高値は130でした(n=20)。
このことから、約半量のダイオキシン類は水田に残っていると考えられます。水田に残っているダイオキシンが今でも環境中に流出していることは、「宍道湖・東京湾の底質コア試料の分析」(姚元ら)からも伺えます。
7. 発生源同定の必要性
先の費用対効果分析や発生源分析は、焼却炉からの排出を減らすというだけでは、限界があるいことを示しています。
他に、よりよい対策はないのでしょうか?実は、少し時間をかけても、経済的な焼却施設対策の方法を模索することが、とても重要です。さらに、ごみ処理システムの検討も不可欠です。
もう一つは、水田対策の検討です。現実的な水田対策があるかどうか分かりませんが、可能性は追求しなければならないでしょう。それでは減らないではないかという疑問をもつ方もおられるでしょう。しかし、発生源がこのような状態なら、ある程度以上は、いくらお金をかけても意味がないのです。
最近の厚生省の発表では、食事からのTEQ摂取量の6割がCo-PCBです。胎児リスクを減らすためには、Co-PCBの削減こそ重要だということです。ところが、今度は、このCo-PCBがどこからくるか分からないのです。
益永は、このCo-PCBの5〜6割は焼却から、残りはPCB製品に起因していると解析しています。焼却から出るといっても、排ガス中の全TEQの中に占める、Co-PCBの割合は、たかだか数%です。ところが、魚介類では、7割もがCo-PCBになるのです。
Co-PCBは、途中で入ってくるのか、或いは、ダイオキシンとの物性の違いから、このようになるのか、まだはっきりしません。いずれにしろ、発生源が分からないままでは、対策はたてられません。
仮に、食事中のCo-PCBの半分程度が焼却炉から排出されているとした場合、今のようにTEQで規制するのが意味があるのかどうかも、疑問です。排ガス中のTEQの内、Co-PCBは数%にすぎないからです。
Co-PCBについては、我々の研究もまた遅れていますが、このような発生源探索研究なしには、効果的な対策はありえないことは、いくら強調しても足りません。そのための科学も必要です。
本ワークショップでは、対象は違いますが、伏見暁洋・梶原秀夫、岡崎聖司らが同様の考え方から、発生源解析の手法開発に取り組んだ結果を発表します。生態リスク研究では、中丸麻由子・巌佐庸がDDTを対象に新しい結果を出しました。
本研究は、科学技術研究事業団の戦略基礎研究推進事業として、援助を受けています。この援助も後1年で終わります。来年までに、さらに大きな結果を出したいです。