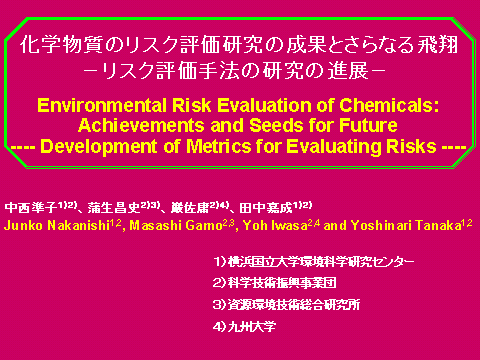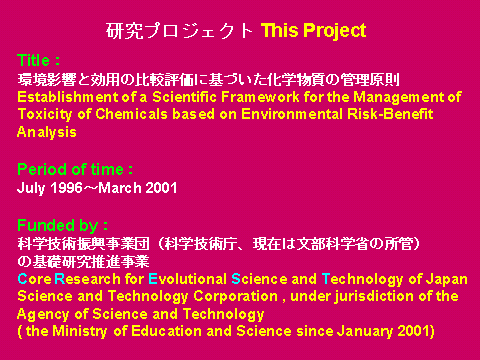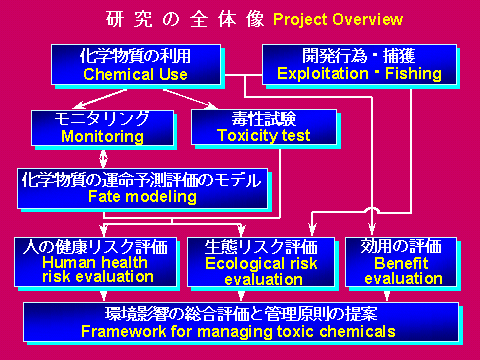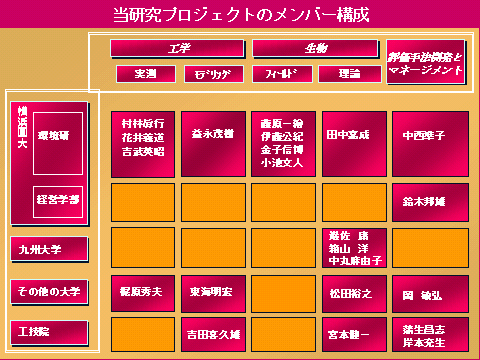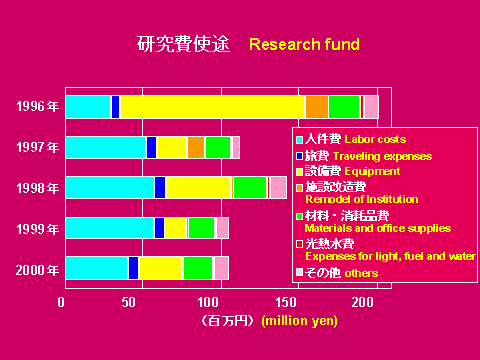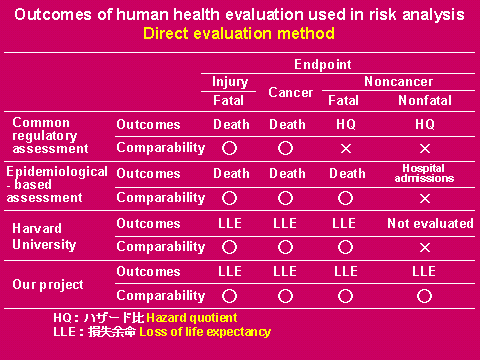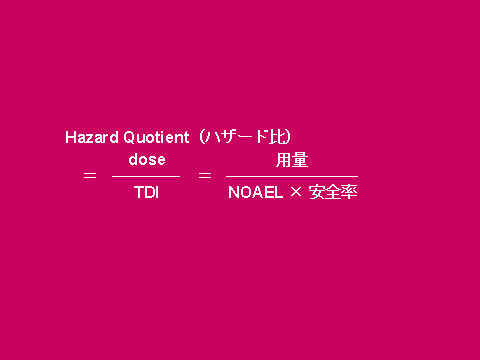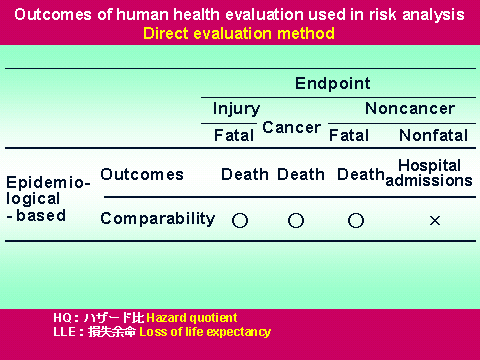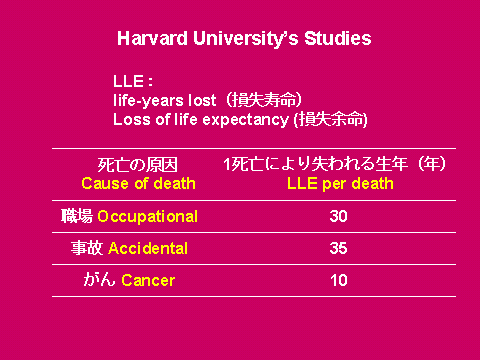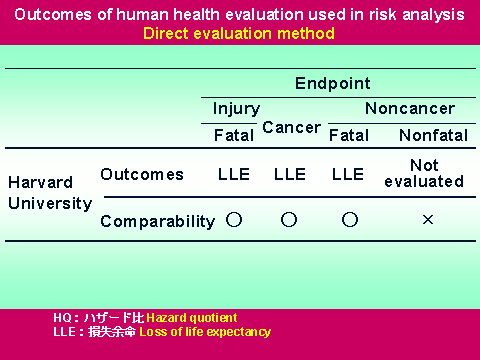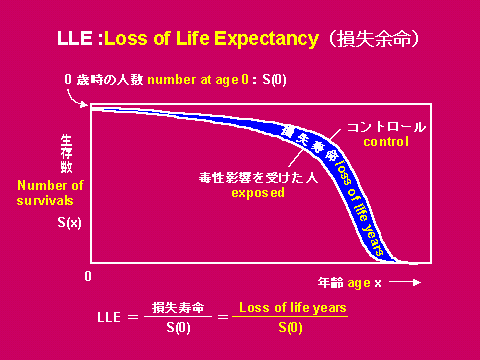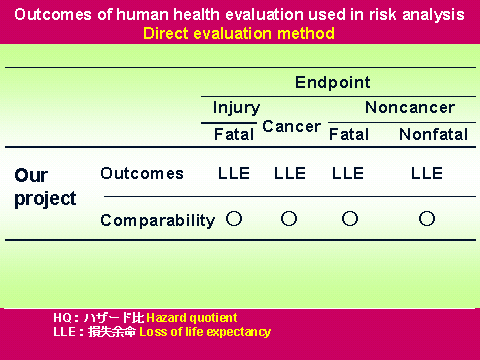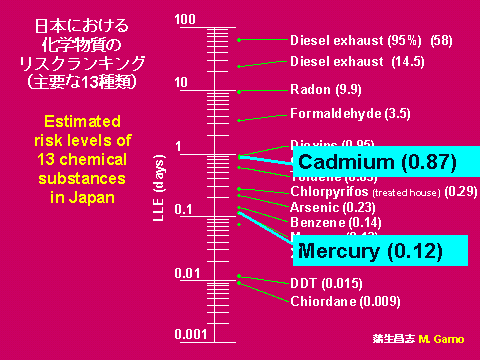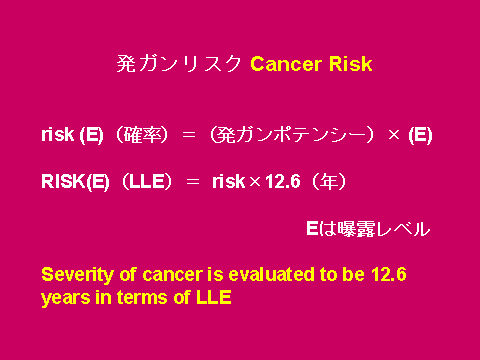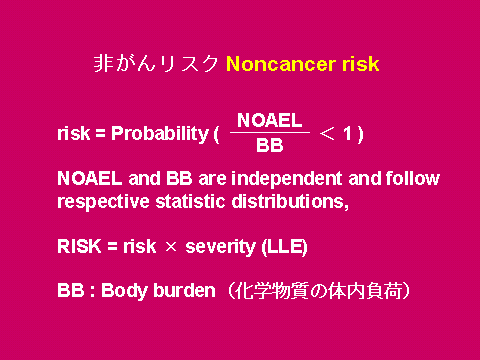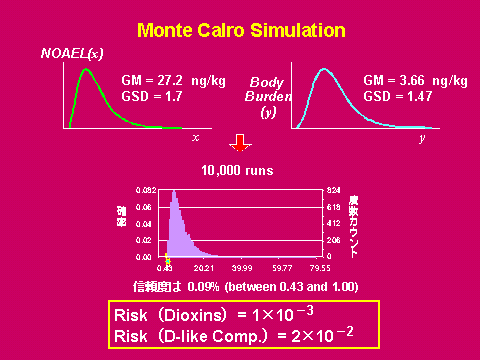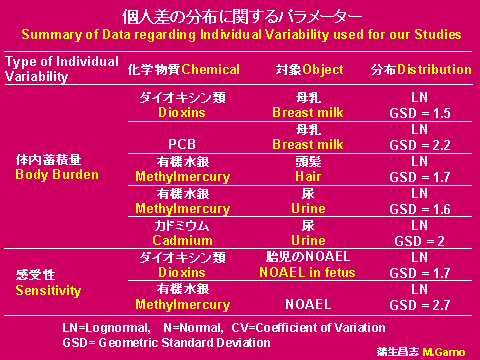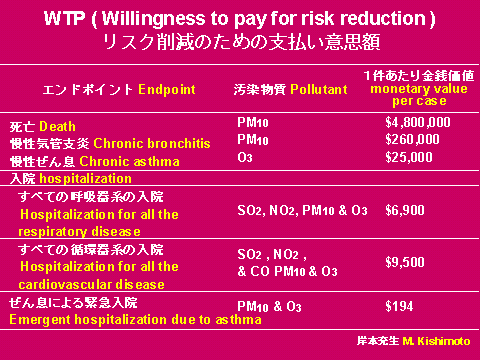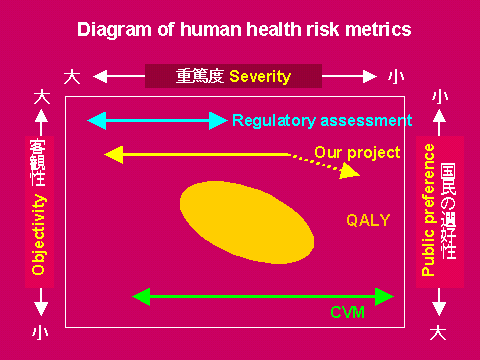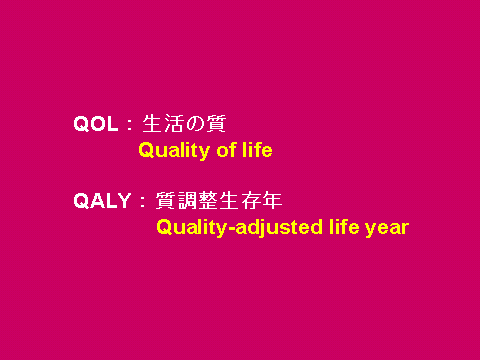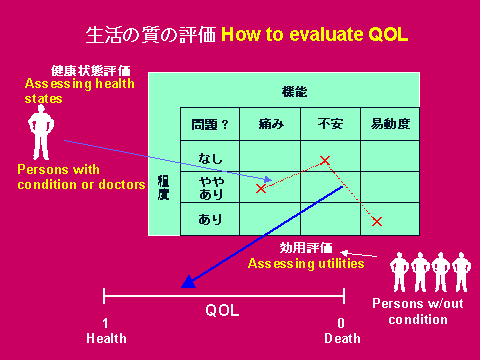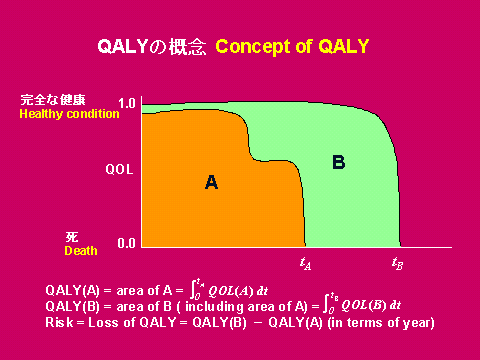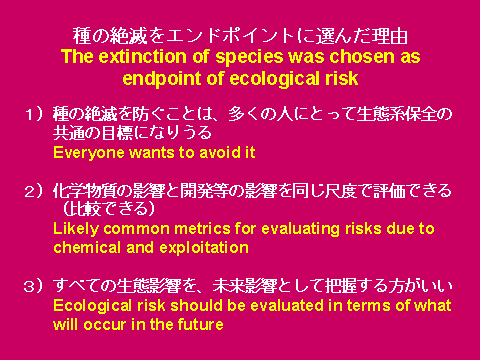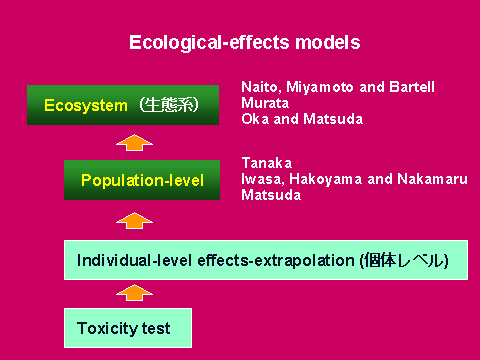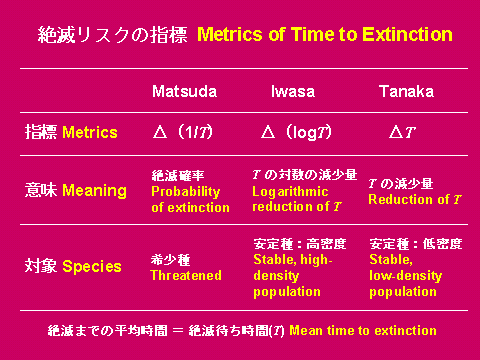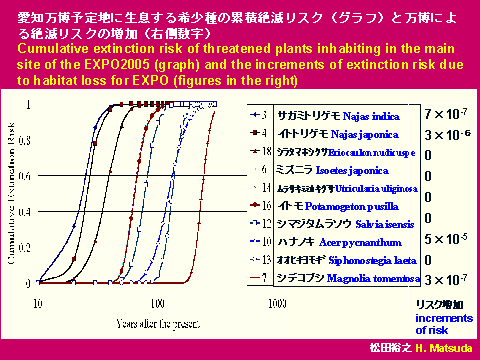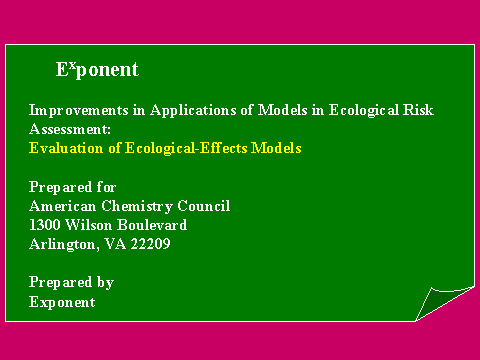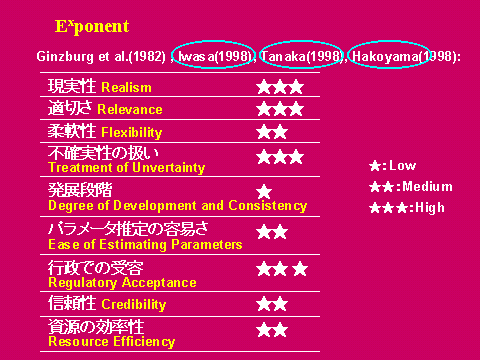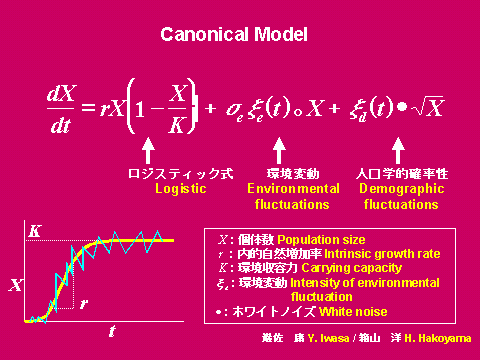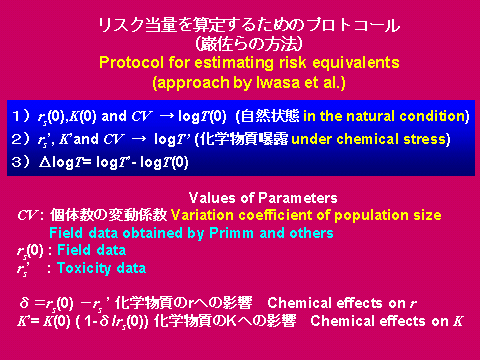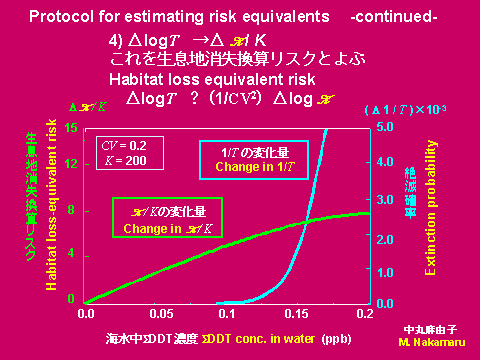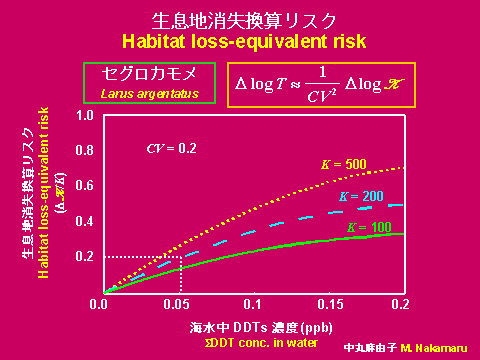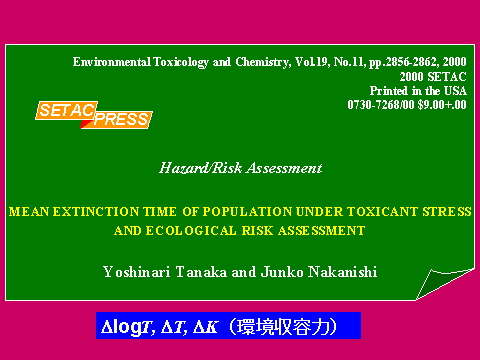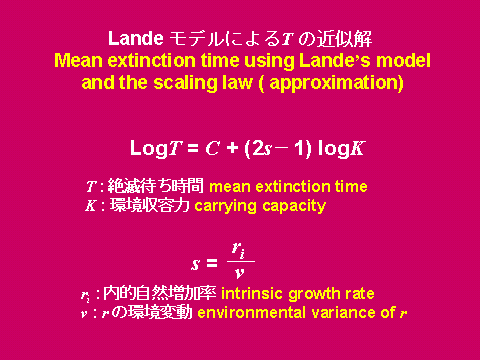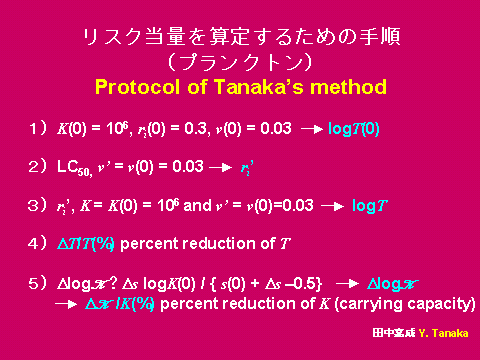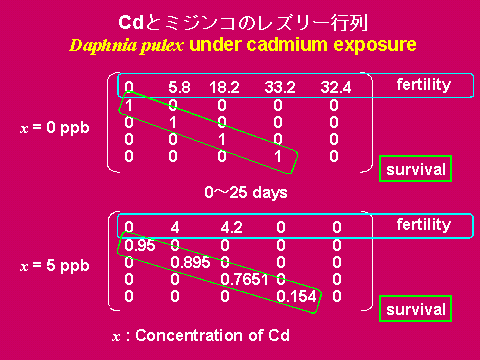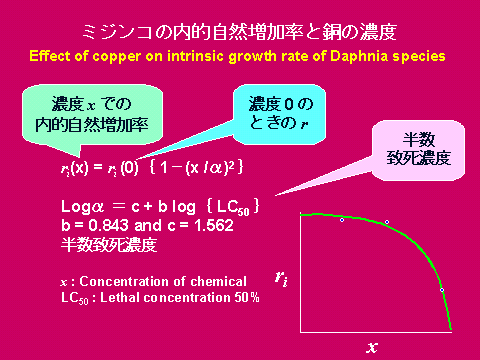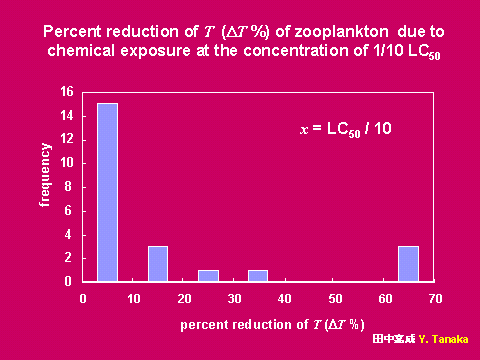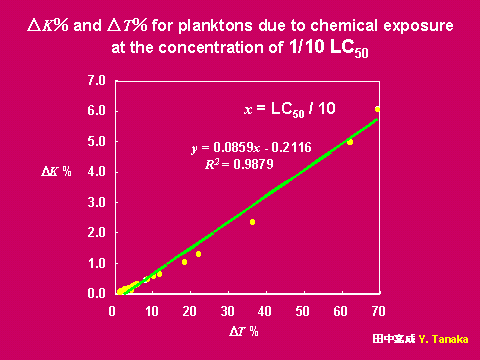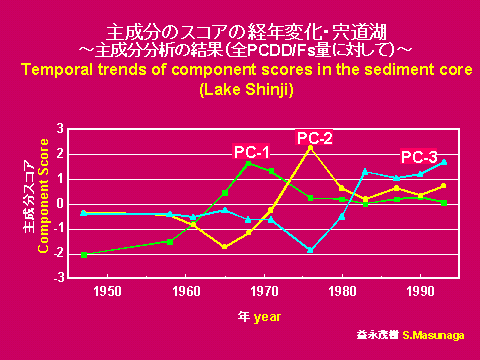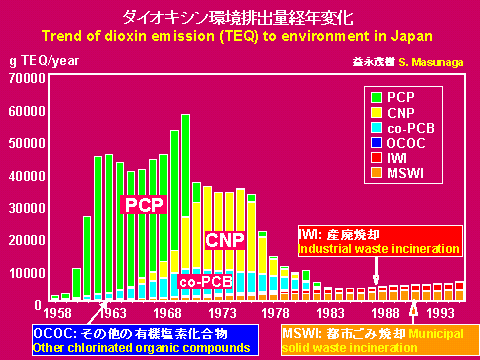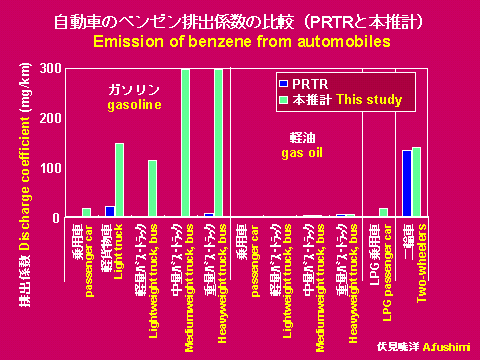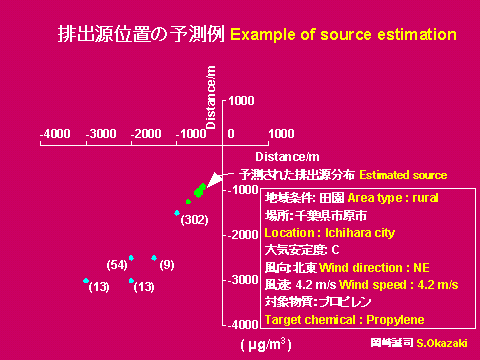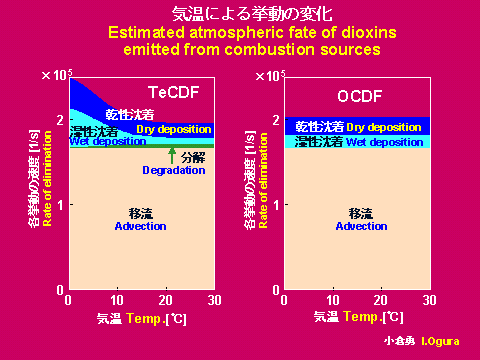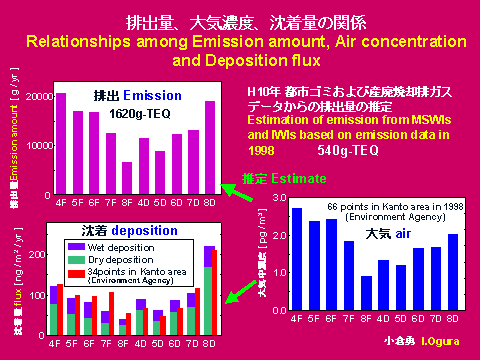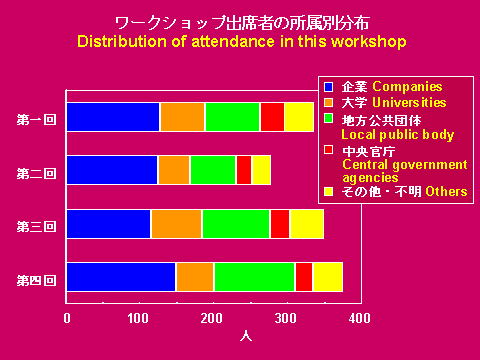|
��S��@���w�����̃��X�N�]���E���X�N�Ǘ��Ɋւ��鍑�ۃ��[�N�V���b�v���\���e �������q�A�������u�A�ލ��f�A�c���Ð�
�P�D�͂��߂�
�@A�Ƃ������w�����ɔ��K����������Ƃ������R�ŋ֎~����A�a�Ƃ����������g����悤�ɂȂ�܂����B�Ƃ��낪�AB�͔Z�x�������Ɛ_�o�n�ɏ�Q��^���邱�Ƃ��������Ă��܂��B���̂Ƃ��AA���֎~���邱�ƂŁA�ǂ̂��炢���X�N�����������̂��Ƃ������Ƃ�m�邽�߂ɂ́A�����X�N�Ɛ_�o�n���X�N�Ƃ���r�ł��Ȃ���Ȃ�܂���B �o�����X�̂Ƃꂽ����Ƃ�A�����́A����̌�����]������ɂ́A���̂悤�Ȉ�������X�N���r�ł��邱�Ƃ��ł��d�v�Ȃ��Ƃł��B �����̌����ł́A�����̓�������A�u�َ�̃��X�N���r�ł���悤�Ȏw�W�̊J���v��ړI�ɂ��Ă��܂����B����́A�č��Ȃǂōs���Ă��郊�X�N�]���Ƃ͂��Ȃ�A����Ă��܂��B�ނ̍��́A�َ�̃��X�N���I�A�q�ϓI�ɔ�r����ړx�͂����Ă��Ȃ��̂ł��B����Ȕn���ȁI�ƊF����͎v����ł��傤�B�ł��A�{���ł��B�َ�̃��X�N����r�ł��Ȃ���ԂŁA�ǂ�����ă��X�N�Ǘ����ł��邩�H�F������^��Ɏv���ł��傤�B����́A���X�N�]�����A����ȉ��̃��X�N�Ȃ���S�ł��Ƃ����A���S���ؖ����邽�߂Ɏg���Ă�������ł��B���S���ؖ����邽�߂Ȃ�A��r���ł��Ȃ��Ă��p�͑����̂ł��B�X�ʁX�Ɉ��S���ؖ������������ł��B �������A��X��project�͍ŏ�����A�َ�̃��X�N���r�ł���ړx�����A���������]���̌n�����A������g���ă��X�N�Ǘ��������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�ڕW�Ɍ������Ă��܂����B���ĂŎg���Ă��郊�X�N�]���̑̌n�ƈႤ���̂�ڎw���Ă������ƁA�����Ĉ��̐��ʂ����������Ƃ������������ł��B �����ŁA�Q�������҂̈ꗗ�ƁA�����������܂��B�islide�T�j
�@�傽�錤�����́A���l������w���Ȋw�����Z���^�[�Ƌ��A����ɍH�ƋZ�p�@�̎����������Z�p�������̏����ł��B������̎g�r�����slide6�Ɏ����ʂ�ł��B
�@�Ȋw�Z�p�U�����ƒc����̌�����́A�T�N�Ԃ̑��z�łقڂV���~�ł��B�傫�Ȏx�o�́A�ݔ���Ɛl����ł��BPD�⌤���⏕���ł����A�T�˂U�l���x������fund�Ōٗp����A���̌������x���Ă��܂����B���̂悤�Ȏ����̎g�������ł���̂��A����fund�̂����Ƃ���ł��B����͂Ƃ������A���ꂾ�����z�̌�������g�킹�đՂ���ł�����A���ʂ��グ�ĊF����ɕԂ��˂Ȃ�Ȃ��A���̈�S�Ŋ撣���Ă��܂����B ���ꂩ��A�{�v���W�F�N�g�����̂T�N�Ԃ̐��ʂ���܂��B�������A���Ԃ����Ȃ��A�ƂĂ��S�̂����b�����邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�����́A���X�N�]����@�̊J���Ƃ�������ŁA�ǂ��������ʂ����������Ƃ������Ƃɘb�����i��܂��B�����A�Ō�ɁA����������������͎�@�J���̌������ʂɂ͐G�ꂽ���Ǝv���Ă��܂��B �Q�D�ЂƂ̌��N���X�N�]����@�i���ږ@�j
�@�����Ɏ����̂́A���N��Ԃڕ]������ړx�ł��B�ԐړI�ɕ]��������@������̂ł����A����͌�ŐG��܂��B���̕\�́A���Q�A����A����ł͂Ȃ����v���I�ȉe���A�v���I�łȂ��e���ɂ��āA�ǂ������w�W�ŕ]������Ă��邩�A����͑��̃��X�N�Ɣ�r�ł��邩�Ƃ������_�ł܂Ƃ߂����̂ł��B�č����Œʏ�s���Ă���A�s���ړI�̃��X�N�]����@�ł́A�v���I�ȏ��Q�́A���S���������ă��X�N��]�����܂��B�����X�N�������ł��B�������A����ȊO�̉e���ɂ��ẮA�n�U�[�h��ŕ]������܂��̂ŁA���̃��X�N�Ƃ̔�r�͂ł��܂���(slide8)�B
�@�n�U�[�h��iHazard�@quotient�j�Ƃ́A�\�I�ʂ����e�ʂŊ������l�ł����A�P����ł�������Ȃ��Ƃ������Ƃ͕�����܂����A����ȊO�̏��͓����܂���B�܂��AHQ���P�ł����Ă��A�Ǐ�̏d�����̂��A�y�����̂�����̂ŁA���X�N��r���ł��Ȃ��̂ł��B ��C������E�ƕa��Ώۂɂ��āA�u�w�����̌��ʂɊ�Â������X�N�]�����s���邱�Ƃ�����܂�(slide9)�B
���̏ꍇ�́A���S���Ɋ�Â��Ă���ȊO�̕a�C�ɂ�鎀�S�����v�Z����܂��B���Ɏ���Ȃ��A���y�ǂ̕a�C�̃��X�N���]������Ă��܂����A���a������@�������Ȃǂ��w�W�ɂ��ĕ]������Ă���A���@�����Ǝ��S�����ǂ̂悤�ɔ�r���邩�ɂ��Ă̌����͍s���Ă��Ȃ��̂ŁA�����̌��ʂ��A���̂܂܂ł́A���X�N��r�Ɏg���Ȃ��̂ł��B �@���E�e���Ő����]�����s���Ă��܂����A������������̂��߂ɁA���ړI�Ȍ��N���X�N�w�W��p�����ꍇ�ɂ́A�v���I�Ȏ��ۂ�������r��]���̑ΏۂɂȂ��Ă���ꍇ�������̂ł��B �@�ŋ߂́A���S���ɂ��Ă��A�l���̏����ɂ����鎀�S�ƁA�l���̏I���ɂ����閝���a�ɂ�鎀�S������Ɉ����Ă��܂����Ƃ͓K���ł͂Ȃ��ƍl������悤�ɂȂ�A���S�ɂ���Ď���������iLLE�j���w�W�ɂ���l�������o�Ă��܂����B�ЂƂ̓T�^�Ƃ���Harvard��w�̌������Љ�ł��܂�(slide10)�B
Harvard��w�ł̌����ł́A���ꂼ��̕a�C���L��LLE��p�����A�����10�N�A�E�ƕa��30�N�A���̂�35�N�Ƃ����悤�ɒP�������Ă��܂��B����A�a�C�̔����ɂ��d�ݕt�������Ă���Ƃ����ł��B �@���̎w�W���g���āA�����̃��X�N�팸��̌o�ό����]�������Ă��܂����A�a�C�̔����ɂ�鎀�̏d�ݕt���͍s���Ă��܂����A�a�C�̏d�ēx�ɑ���d�݂Â��͍s���Ă��炸�A�܂��A�]������Ă���̂͒v���I�ȃP�[�X���A�����قƂ�ǂƂ����̂����Ԃł��B �@�������́A��ނ̈قȂ�l�̌��N���X�N��]�����邽�߂ɁALLE�i�����]���j�Ƃ����ړx��p����̂������Ǝ咣���āA���̌������n�߂܂���(slide11)�B
LLE�Ƃ����_�ł́AHarvard�@��w�Ɠ����ł����A���e�͑傢�Ɉ���Ă��܂��B�����approach�́A�a�C�̏d�ēx��]�����邽�߂ɁA�a�C����LLE��p���邱�ƁA����ɁA�v���I�łȂ��a�C�ɂ��Ă��A�a�C�̋ꂵ�݂��琶��������Z�k��]�����悤�Ƃ�����̂ł�(slide12)�B
�܂�A���Ɏ���Ȃ����X�N�ɂ��Ă��A�v���I�ȃ��X�N�Ɠ����ړx�ŕ]�����悤�Ƃ�����̂ł��B����ȊO�ł́A��r�������Ȃ����P�[�X�́A���`�����⒆�ŁiSMR�f�[�^�Ɛ����\�j�A�N�����s���t�H�X�i��f���ʂƎ��S���j�A�J�h�~�E���A�g���G���Ȃǂɂ��e���ł��B �@�����̕]���@�́A�v���I�Ȃ��̂������Ă��Ȃ��Ƃ����ᔻ����ɂ���܂������A����͌���ł��B���̌���́ALLE���v���I�ȉe���݂̂�]������ړx�Ƃ��Ďg���Ă������Ƃ���A�o�����̂Ǝv���܂��B�ނ���A��X�̕]����@�́A���ڕ]����@�ł́A���E�ŗB��َ�̃��X�N���r�ł�����̂Ȃ̂ł�(slide13)�B
�R�D�������u�̌���
�@�����{�l���������܂��̂ŁA�����ȒP�ɐ������Ă����܂��B���ϓI�ȓ��{�l�̏W�c�ɂ��Ẵ��X�N�ł��B�c���́A���X�N��LLE�̓��P�ʂŕ\�������̂ł��B���̒��ł́Adiesel�r�K�X�ɂ�郊�X�N����ԍ����ł��B�������A�����diesel�ɂ��x���̃��X�N�݂̂ł��B �@���������Ɋ܂܂�鉻�w�����́A�P������10-5�̔����X�N�ŋK������Ă��邱�Ƃ������ł����A10-5�̃��X�N�́ALLE��0.05���ɑ������܂��B�����ɂ́A�����X�N�ȊO�̃��X�N����������܂��B�J�h�~�E���R��A���₵����ł��B����������r�́ALLE���ړx�Ƃ����X�̊J��������@�������Ă͂��߂ĉ\�ɂȂ����̂ł��B �S�D�l�̌��N���X�N�]���̃v���g�R�[��
LLE���ړx�Ƃ��郊�X�N�iRISK�j�Z��̂��߂̃v���g�R�[�����A�ȉ��̂S�P�[�X�ɂ킯�Ă܂Ƃ߂܂����B �@�܂��A�����X�N�Z��̎菇�����b���܂��islide16�j�B
�@�ʏ�A�����X�N�͊m���ŕ\������܂��B���ꂪ�A��������risk�ł��B�����ŁAE�͖\�I�ʂł��BE�̑����BB�Ƃ����̓����חʂ��g�����Ƃ�����܂��BLLE���ړx�Ƃ��郊�X�N���A�啶���ŏ����܂����B������A�Z�o���邽�߂ɂ́A�����ɂ��̕a�C�̏d�ēx�������A12.6�N��������̂ł��B����ɂ���l�̎���12.6�N�̎����Z�k�������炷����ł��B �@���ɁA�X�N�ł��B�p�ʔ����W�������炸�ANOAEL�i����p�ʁj�݂̂���������Ȃ��ꍇ�̕��@���A�������܂�(slide17)�B
�@���̂Ƃ��́A�\�I�ʁA���͑̓����חʂ�NOAEL�i����p�ʁj���銄�����A�m���Ƃ��Ẵ��X�N�ł���ƒ�`���܂��B����́A���X�N�̉ߑ�]���ł����A���ꂵ����Ȃ��̂ł�ނ����܂���B���ł́ANOAEL�^BB���P�ȉ��̊m���ƂȂ��Ă��܂����A�����Ӗ��ł��B���̊m����Monte Carlo�@simulation�ŋ��߂�̂ł�(Slide18)�B
���̂Ƃ���ԑ�ȓ_�́A�\�I�ʂɂ����z������A���ɂ����z������Ƃ����F���ł��B������������́A�l���Ƃ��s�m�����Ƃ�т܂��B����������ƁA�X�N�]���ł́A���̌l�����ǂ̂悤�Ɍ��邩���|�C���g�Ȃ̂ł��B�܂�A���܂��܋������I�����l�A���܂��܊��������l�̊��������X�N�Ȃ̂ł��B���̂悤�ɂ��ċ��߂��m�����X�N�ɁA���̕a�C�̏d�ēx�iseverity�j��������ALLE��P�ʂƂ������X�N�����߂���̂ł��B �@severity�̒l�̋��ߕ��ɂ��ẮA�����������A�ڂ������܂��B�l���̕��z�́A���X�N�]���ŏd�v�ȃp�����[�^�ł��̂ŁAProceedings��Table A1�Ɏ����܂���(slide19)�B
5�D�l�̌��N���X�N�]���i�Ԑږ@�j
���̎w�W�́A���X�N�̑傫�����q�ϓI�ɕ\��������̂ł͂Ȃ��̂ŁA�҂Ƀ��X�N�̑傫���ɂ��Ă̗\���m�����Ȃ��ꍇ�́A�\�╵�͋C�ɍ��E�����v�f�͑傫���̂ł��B�������A�Љ��ł́A�����̍�����������������Ă��郊�X�N�̑傫����m�邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ŁA���̓_�ł́A�����_������܂��B��X���A�Ȃ����̕]����@���g��Ȃ��������ɂ��ẮA�����A���@�q�O�����܂��B �@������x�A�l�̃��X�N�]���̎ړx�ɂ��čl���܂��傤�B���̐}�����Ă��������islide21�j�B
�@�ʏ�K���ɗp�����Ă���]���̎ړx�́A�q�ϓI�ł͂���܂����A����ƒv���I�ȉe��������r�͂ł��܂���B��X�̕��@�́A���ׂĂ�ԗ�����Ӑ}�ŊJ�����܂������A�Ǐ�̌y�����̂ɂ͓݊��ŁA��͂����ł��B����ACVM�ɂ����@�́A�y�ǂ̉e�����]���ł���_�ł����ł����A�q�ϓI�ł͂���܂���A������d���e���̕]���Ɏg���̂͊댯�ł��B�������A����ŁA�q�ϓI�ł͂Ȃ����A���������ړx�������̍D�݂f���Ă���ƌ����_�́A�ǂ��_�ŁA�������܂���B �@���ږ@�ƊԐږ@�̒��Ԃɂ����@�Ƃ���QOL�i�����̎��j���g���������̎����������N�iQALY�j�Ƃ����w�W����w�̕���ɂ���܂�(slide22)�B
���ꂪ�A�����ł��L���g���钛��������A��X���܂��A����ɒ��ڂ��Ă��܂��B���̈ʒu�Â��ł́A���̐}(slide23)�̒��ԂɈʒu���ALLE���A�y�x�̏Ǐ��]������ɂ͊��x�������Ƃ������_��₢�A�Ȃ����ALLE�Ƃ̊֘A�����₷���ƍl���Ă��܂��B�������A�{���Ɏg���邩�ۂ��́A���ׂĂ݂Ȃ��ƕ�����܂���B �@QOL�̋��ߕ��̌�����������܂��BQOL�ɂ͑����̎�ނ�����܂����A���̂ЂƂ̐����}�ł��islide24�j�B
�@���̂悤�ɂ��ċ��߂�ꂽQOL���g���A����ɕa�C�̔N����������ƁA�����������N�iQALY�j�����߂��܂��islide25�j�B
�@������A�g���ƁA�ʐςa�|�ʐ�A�̍������X�N���Ƃ����������ŋ��߂邱�Ƃ��ł���̂ł��BtA��tB�Ƃ̍��́A��ɏq�ׂ�LLE�ł��B �@���X�N�]���ɂ��܂��A�s���̑I�D���傫����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝ������͍l���Ă��܂��B�������A����ŁA�s���̔��f���x���邽�߂́A�ł��邾���q�ϓI�Ȕ��f�ޗ����K�v�ł��B�����łȂ���A���]��Q�����o����ł��傤�B���̈Ӗ��ŁA�����́A�s���̑I�D�x�ƁA��͂艽�炩�̋q�ϓI�ȃ��X�N�ړx�Ƃ�����������V�X�e������낤�Ǝv���̂ł��BQOL�́A���̈Ӗ��ŁA���Ȃ莩�R�ɐv���ł��܂��B���ɐv���āAQALY��WTP���������]���ɂǂ̂悤�Ɏg�����A��X�̍���̉ۑ�ł��B�@�@ �@���́A���ԃ��X�N�w�W�̘b�ł��B �U�D���ԃ��X�N
����́A�����Ɏ������R�ɂ����̂ł��B
�islide28�j���ԉe���]�����f���́A��ʂɌ̃��x���Apopulation���x���A�G�R�V�X�e�����x���ɒi�K�I�ɕ��ނ���Ă��܂����A���̘g�g�݂̒��ōl����ƁA�����̌����́Apopulation���x���ł̉e���]���i�ލ��f�A���R�@�m�A���ۖ��R�q�A���c�T�V�A�c���Ð��j���f����ecosystem level ���f���ƈʒu�Â����܂��B�{���͎��Ԃ��Ȃ��Ă��b���ł��܂��A�G�R�V�X�e�����f���ł́A��ԑ��ݍ�p�i�{�{����A�����@�q�j�A�H���A���ɔ��������Z�k�A��̐��Ԋw�I�d�ݕt���i���@�q�O�j��������܂����B�킪���Ő��ԃ��X�N�]���ƌ����Ă�����̂́A�̃��x���̓Ő��]���ɂ����܂���B�������ꂩ�炨�b������A��Ń��X�N��population-level�̉e���]�����f���ł��B �@��Ń��X�N�̌����́A�܂��A��ő҂����ԁAT���ǂ̂悤�ɐ��肷�邩����A�n�܂�܂����islide29�j�B
��Ŋm����1/T�ł�������A�����̃v���W�F�N�g�́A����1/T�Ő��ԃ��X�N��]������Ƃ����l���ł����B�������A�����A�ލ����ڂ����q�ׂ�悤�ɁA1/T�̎ړx�́A��ɂ��ẮA���̃��X�N��\������ɓK�Ȏw�W�ł����A�̐��̑�������Ȑ�����ւ̉e����]������ɂ́A���܂�ɂ��݊��Ȏw�W�ł��邱�Ƃ��������Ă��܂����B�����ŁA�����́A��ɂ��Ă�1/T���A����Ȏ�ɂ��Ă�logT������T���̂��̂��ړx�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂����B�O�̎ړx�ɂ��Ă̌��ʂ��A���ꂩ��q�ׂ܂��B
�V�D���c�T�V�̌���
�@�ڂ����́A�����{�l�����\���܂��B����́A���m�������\�肳��Ă���C��̐X�ɐ��������ɂ��Ă̌v�Z���ʂł��B���̐}���A���̎�̐�Ŋm���ł��B�E�̐��l���A���m�����̎��{�ɔ������ؽ��̑������ł��B�����A�V�f�R�u�V�����ɂȂ�܂������A�ނ����Ԃ��ԂȂ��̂̓T�K�~�g���Q���ł��邱�Ƃ�������܂��B�܂��AEXPO�ɂ�郊�X�N����ԍ����̂́A�n���m�L�ł��B���������ƁA���m�����̍ۂɉ��ɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������悭������܂��B �W�D�ލ����approach �@�ŋ߁A�č��́AExponent�ЂƂ����R���T���^���g���A�č����w�ψ���̋��߂ɂ��A���ԉe�����f���̌���ƕ]���ɂ��Ă̕����܂Ƃ߂܂����islide31,slide32�j�B
���̒��ŁA��X�̌����O���[�v�̌����͍����]������Ă��܂��B�ލ���Ɠc����̌����́A�̌Q�e���]�����f���́Ascalar�@abundance�@model�̒��Ɉʒu�Â����A���̕]���́A���̐}�Ɏ����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�O�����ǂ��A��͂��߂Ƃ������Ƃł��B �@�����ł́A�܂�Iwasa��̌����ɂ��ĕ��܂��islide33�j�B
�@�ڂ����́A����Iwasa���g�����b�����܂��̂ŁA�����ł͂���肾����b���܂��B �@Iwasa��́A�̐��i�w�j�̎��ԕω�����I���R�������ir�j�A�����e�́iK�j�A���ϓ��i��e�j�̎O�̃p�����[�^�ŋL�q����m�������������̊�{�����Ă��܂����B���I���R������r�͂��̌��z�AK�͕��t�̌̐��ł��B����ɁA����ɉ��w�����ɂ��e�����q�i�j�������āA���w�����̉e�����ł̌̐��w�̎��ԕω���\�����鎮����o���܂����islide34�j�B
�@�����ŁA���R��Ԃł� ���I���R�������irs(0)�j�A�����e�́iK(0)�j�A�ƌ̐��̕ϓ��W���iCV�j�̒l������A��ő҂����ԁiT(0)�j�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B �@���ɁA���w�������݉��ł̓��I���R�������irs'�j�� K'�ACV�̒l���^������AlogT'�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B�������āA���w�����̔��I�ɂ��T�̒Z�k�ʂ����߂��܂�(slide35)�B
�@Iwasa�炪��o��������p����ƁA��logT����A����ɑ������郢�j�^-K���Z��ł���̂ł��B������A�����e�͊��Z���X�N�A�����n�������Z���X�N�A�����͒P�Ƀ��X�N���ʂƂ�Ԃ��Ƃɂ��܂��傤�B�܂�A��ő҂����Ԃ̕ω����A�����n�T�C�Y�̏����ʂƂ��ĕ\���ł����̂ł��B�������A��K��rs(0)��rs'�ɕω����邱�Ƃɂ���Đ�����K�̌����̕ω��ʂł͂Ȃ��A�����܂ł����z�I�Ȓl�ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B���̈Ӗ��ŁA���̂�ς��܂����B �@�����܂�K�̌������n�̌����ƌĂ�ł��܂����B����́A�ʐς̌����ɒl����Ƃ͕K�����������܂���B�\���L���ʐς̂Ƃ���ł́AK�̌����͖ʐς̌����ɑΉ�����ł��傤�B�������A�ʐς��������Ȃ�ƁA�ق�̏����̖ʐς̕ω���K�͋}���Ɍ������܂��B�����������Ƃ��l���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �@Slide35�́A�����n�������X�N�Ƃ��ĕ\���������ƁA1/T�ŕ\���������̈Ⴂ�������Ă��܂��B1/T�A�܂��Ŋm���ŕ]������ƁA�Z�x�̒Ⴂ�Ƃ���̓[���ɂȂ��Ă��܂��܂��B�������A��K/K�Ō���ƁA�����n�����������Ɠ����悤�ȕω��������Ă���̂�������܂��B�������������ȕω������߂������A�������A���̃��X�N�Ɣ�r���Ǘ����s���ɂ́A��K�^�j���L�����ƍl���Ă���̂ł��B �@���ۂ�́ADDT���Z�O���J�����ƃn�C�^�J�ɗ^���鐶�ԃ��X�N���A���X�N���ʂƂ����������ŎZ�肵�A������܂��B�ڂ����́A�����̕������Ă��������܂����A�����ł́A�Z�O���J�����ɂ��Ă̌��ʂ��ꖇ�����}�ŏЉ�܂�(slide36)�B
�����͊C������DDT�Z�x�ł��B���̎��̃��X�N���ʂ��c���ł��B �@�����Ő����n20�������ɑΉ�����C�����Z�x������Ɍ��߂�Ƃ����悤�Ȍ��ߕ����\�ł��B�Ȃ��A20���Ȃ̂��Ȃǂɂ��ẮA�܂��ʂ̋@��ɍl���܂��傤�B�����A���̌��ʂ��炷���Ɍ��_���o���قǂɂ́A�����͐��n���Ă��܂���B���̌��ʂ����đՂ��ƕ�����܂��悤�ɁA���̌��ʂ�K�̒l�ɑ傫���ˑ����Ă��܂��B�������AK�̒l��m�邱�Ƃ͈�ʓI�ɔ��ɓ���ł��B���̂��Ƃ��l����ƁA�܂��܂��������s�\���Ȃ̂ł��B �X�D�c�����approach
���������Ȍn�ł����AK��100���ɂ��Ȃ�AIwasa��̑ΏۂƂ͐����Ⴄ�̂ł��B���A�ލ���̕��@�ƁA�c����̕��@�Ƃ̔�r���AProceedings��Appendix�ATable A2�i�p���j�Ɏ����܂����̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������islide38�j�B
�@�c����́ALande�̎��ƃX�P�[�����O�����g���āA��ő҂�����(T)�Ɖ��w�����Ƃ̊W�������܂����B���̏ꍇ�A��ő҂����ԁiT�j�́A���I���R������ri(0)�A�����e��K�Ƃ���ɁAri�̕ϓ��W�������狁�߂邱�Ƃ��ł��܂��B���̌��ʂ�Iwasa��̌��ʂƔ��Ɏ��Ă��܂��B���҂͂��̊�{���i�ŗގ��_������܂����A�������̈Ⴂ������܂��B�܂��ALande�̊�{���ł̓��I���R��������Iwasa��̂���Ƃ́A�����Ӗ����Ⴂ�܂��B���̂��߁AIwasa��̎��̂��ɂ�s�̓Y���������ATanaka��̂��ɂ�i�����܂����B�ڂ����́AProceedings�t�^��TableA2�����đՂ������Ǝv���܂��B�Ȃ��A�Ⴄ���A�ǂ��炪���������Ƃ����^����F���������ł��傤���A���̂悤�Ɏ�����`�I�Ɍ��܂�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ƍl���Ă��������B�����A�����ǂ��炪�g���₷�����͋c�_�����ł��傤���A�ǂ��炪�������Ƃ������Ƃ͂��܂�c�_����Ȃ��Ǝv���܂��islide39�j�B
�@Lande�̎��ʼn��w�����̉e�����ł�ri'�����߂邱�Ƃ��ł���A���w�����̉e�����ł̐�ő҂����Ԃ����߂邱�Ƃ��ł��܂��B �@�������A���w�����ɔ��I���ꂽ���̓��I���R������ri'�����߂邱�Ƃ͎��́A�ƂĂ���ςȂ��Ƃł��B�܂��A���������l�����߂邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ��������Ȃ��̂ł��B���w�������I�̉e��������Ƃ���ri'�����߂邽�߂ɂ́A�����̔N��ʂ̓Ő��f�[�^���K�v�ł��B�܂�A���̐}�islide40�j�Ɏ����悤���Y���[�s��̒l���A���ꂼ��̉��w�����̔Z�x�ɂ��ĕK�v�Ȃ̂ł��B
�@Tanaka��́A��ɓ��邾���̕����ׁA���w������r�Ƃ̊W������Ă�����́A�y�сA�v�Z�����r���v�Z�ł��镶�����47��E���o���A���w�����̔Z�x��r�Ƃ̊W�����܂����B���������͂قƂ�ǂ������v�����N�g���A���ł��~�W���R�ł��B �@���̌��ʁA�v�����N�g���ɂ��āA���̐}�islide41�j�Ɏ����悤�ȊW�������t���܂����B
�@�܂�A���w�����̔Z�x��x�̂Ƃ��́A���I���R������ri���A�}���Ő��l��LC50�l���狁�߂��A�����̂ł��B�����I�Ȏ��_���猩��ƁA���̉�A���͋ɂ߂ďd�v�ł��B�}���Ő��l��LC50�̒l�́A�͂��Ď̂Ă�قǂ���܂��B������g���Ari(0)�����������Ă���Ari'�̒l������ł���̂ł��B�����A���̊W�́A��Ƃ��ă~�W���R�ŋ��߂����̂ł��B���̐�����łǂ��Ȃ邩�́A����̉ۑ�ł��B �@23�̌n�ɂ��āALC50�l��1/10��1/100�̔Z�x�ł́A���w�����ɂ��T�̌������ƃ��X�N���ʃ�K /K�̌��������A�c�����v�Z�������ʂ�Proccedings�Ɏ����܂���(slide42, slide43)�B
�����n�������Z���X�N�́AT�̍팸����1/10���x�ŁA������͏��������Ƃ�������܂��B�܂�A�����̃v�����N�g���ɂƂ��āALC50��1/10�̔Z�x�Ő������邱�Ƃ́A�����n����������0.�P�����x�������郊�X�N�ɓ������Ƃ������Ƃł��B�������������A�\���傫�Ȑ��ʐς̂���Ƃ���ɁALC50��1/10���x�̗L�Q����r�o����ƁA����́A�����n�𐔁�����P�����x���ߗ��Ă����Ɠ������x�̃��X�N������Ƃ������Ƃł��B�����ł͖ܘ_�����Șb�����Ă���킯�ł͂���܂���B��܂��Ȍ����������Ă���̂ł��B�����ŁA�d�v�Ȃ��Ƃ́A�c����̌����ŁA�̃��x���̓Ő��f�[�^���Apopulation-level�̉e���\���Ɏg���铹���J�������Ƃł��B ����ɂ��A������LC50�ɈӖ������炩�ɂȂ�܂����BLC50�̐��Ԋw�I�ȈӖ��́A������ɂ���đ傫���قȂ�ł��傤�B���̐�����ł��A�����悤�Ȃ��Ƃ��ł���ALC50�l�̐�����ɂ��Ӗ��̈Ⴂ�A�܂��A�ǂ̂悤�Ɏg���ׂ��������炩�ɂȂ�܂��B����͂��̕�����J�������Ǝv���܂��B�@ �@�����́A���w�����̉e���ɂ���ő҂����ԁi�s�j���Z�o���邽�߂̗��_�I�Șg�g�݂��J�����܂����B����T���x�[�X�ɂ��āA���i1/T�j�A��T/T�A��logT�̎O�ԃ��X�N�]���̎w�W�Ƃ��đI�т܂����B���̎O�̂����̂ǂꂪ�K�����́A�ǂ��������Ԍn��ۑS���������̖ڕW�ɂ���Č��܂�̂ł��B�����̌n�ŁA���w�����̔Z�x�ƁA����T�Ƃ̊W�ɂ��Ă̎Z�莖��𑝂₵�A�����̐l�����Ԍn�ۑS�ɂ�����ڕW�ƁA�ǂ̎w�W���K�����邩���������Ȃ���Ȃ�܂���B�����A��{�͐�ő҂����Ԃ��Ƃ������Ƃł��B �@�����̎���𑝂₷���߂̏�Q�̈�́A���̌v�Z�ɕK�v�ȃp�����[�^�������ɂ������Ƃł��B���̓_�ɂ��ẮA�K�����������œ���̂ł͂Ȃ��A�ʂ̗��_���琄�肷�铹�����㌟������\��ł��܂��B�p�����[�^�̎����l��҂��Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł��B �@���ԃ��X�N�]���̌��ʂ�p�����A���X�N�x�l�t�B�b�g��͂���ɂ��čs���܂����B��́A����ɂ�钆�r���J���̎���A�����ЂƂ�DDT�̎g�p�Ɋւ�����̂ł��B�����A�����I�Ȃ��̂ł����A���ԃ��X�N�]����@�̊J���ƂȂ��ŁA����͂��̕��ʂ̉�͎���𑝂₵�����ƍl���Ă��܂��B���̂��Ƃɂ���āA�l�̌��N���X�N�ŁA�m���I�Ȑ����̉��l�Ƃ����l�����Ƃ߂��Ă���̂Ɠ����ȁA�l�X�̑I���ɉB�ꂽ�A�u���Ԍn�̌o�ω��l�v�𒊏o�ł��锤�ł��B �@��X�̍ŏI�ڕW�́A�����]���ł����A����ɂ��Ă͉��@�q�O�̖����̕��đՂ������ł��B 10�D��������� �@��������������m�邱�Ƃ́A���X�N�Ǘ��ōł��d�v�Ȃ��Ƃł��B�������A�킪���ł͂��ꂪ�s���ʂ܂܁A�N�����s�s���ݏċp�F����_�C�I�L�V����85���o�Ă���ƁA����Ői��ł��܂��܂��B���낵�����Ƃł��B �@�������́A��������͎�@�̊J���Ƃ������ƂɁA�傫�ȗ͂𒍂��ł��܂��B�܂�A�����甭������\������Ȋw�����o�����Ƃ����̂ł��B�����ł́A���̃v���W�F�N�g�ōs�����S������A���ʂ̂�slide�ő�}���ŏЉ�܂��B �@��́A�v�i���s�����_�C�I�L�V���̔�������͂ł��B����́A�����̑͐ω��D�̃R�A�T���v���ɂ��ẮA�听�����͂̌��ʂł��B�O�̎听�������o����܂����BPCP�ACNP�̐��c�����܁A�Ōオ�ċp�ł��islide45, slide46�j�B
�@����������������ɁA�킪���̃_�C�I�L�V���r�o�ʂ̌o�N�ω��𐄒肵�܂����B �@���́A���s�Ŏ����Ԃ���r�o�����x���[���̔Z�x�𐄒肵�����̂ł��B���m�ے��P�N�̕����̎d���ł��BPRTR�@�Ƃ����@�������N�x����{�s����A��Ƃ͉��w�����̔r�o�ʂ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����́A�����ԓ��̖ʓI����������̔r�o�ʂ���Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂�pilot���Ƃ��s���A���������܂����B��X�́A���ꂪ�����̐����̂P�ł��邱�Ƃ��A�����ƃ��f�����O�Ŗ��炩�ɂ��܂����islide47�j�B
�@����́A��͂蔎�m�ے��P�N�̉��萹�i�̎d���ł��B���Z�x�𑪒肷�邱�Ƃɂ���āA�ǂ�����ǂ̂��炢�r�o����邩�𐄒肷��������l���܂����B����́A�s���s�̎���ł��islide48�j�B
�@�Ō�͔��m�ے��R�N�̏��q�̎d���ł��B�ނ́A�Ȗ��Ȏ����ƃ��f�����O�ŁA���Z�x����֓��n���̃_�C�I�L�V���̑��r�o�ʂ𐄒肵�܂����B1998�N�x��1660g�Ɛ��肵�Ă��܂��B�����̕�540�O�����ł��B�������덷�̌����͕K�v�ł����A����ł��\���g����Ǝv���Ă��܂�(slide49, slide50)�B
���̂悤�ɒN���o���Ă���̂����͂����肳���邱�ƁA��Ƃ�r�o�ҕƂ͕ʂɁA�����Z�x���甭���ʂ�m�邱�Ƃ́A���Ǘ��ŏd�v�ȑ����ł��B���̕���ŁA��X�͑傫�Ȑ��ʂ��グ�܂����B �@WS�͍��N�łS��ڂł��B�����̂̕��̎Q���҂������̂ɋ����܂�(slide51)�B
�����̂̕��́A���݂ɂȂ��ċꂵ�݁A�����������@�_��g�ɕt�������Ǝv���Ă���̂��Ǝv���܂��BWS�͍��N�ŏI���ł����A������A���̎����̂̕��̗v�]�ɉ�����悤�Ȃ��Ƃ͎��{�������Ǝv���Ă��܂��B �@���Ò����肪�Ƃ��������܂���(slide52)�B
|